不成就日(ふじょうじゅにち)は何事もうまくいかない日だといわれます。
インパクトのあるネーミングのせいでカレンダーや暦に「不成就日」の文字を見つけると不吉に思ったりしてませんか?
何かを始めたり、大切なイベントを行ったりするのに適さない日とされてきた不成就日ですが、近年では気にしない人も増えています。
不成就日はじつは由来もあいまいで歴史の浅い凶日です。信憑性はありません。インパクトの強い名前のおかげで現代人が使ってるようようなものです。
もちろん「迷信だから信じないよ。」と言える人はそれでいいんです。
でもこの記事を呼んでいるあなたは「迷信だから気にしない」とは言い切れずに迷っているのではないでしょうか?
そんなあなたのために不成就日を気にしなくていい理由を紹介しましょう。
この記事では不成就日を気にしなくていい理由を詳しく掘り下げ、不成就日を気にしないためのヒントをたくさん紹介します。
もう不成就日は気にしなくていいのです!
あなたの人生をもっと自由にもっと豊かにするために、一緒に不成就日と向き合っていきましょう!
1. 不成就日とは?その真実
カレンダーで見かける「不成就日」。ちょっぴり不安になる、という方もいるかもしれませんね。これは「何事も成就しない日」として知られているお日柄です。
不成就日ってどんな日?
簡単に言うと、何か新しいことを始めたり、大切な行事を行ったりするのに向かないとされる日です。「うまくいかないかも…」と感じてしまう、そんな意味合いを持っています。
実は新しい?その由来と歴史
でも、この不成就日、実は古くからのものというわけではないようです。平安時代など、昔の人々も吉凶を気にしていましたが、その時代の公的な暦には、不成就日の名前はなかったのです。
不成就日は、もう少し後の時代になって、民間の間で生まれたという説があります。意外にも、歴史の浅い凶日なのですね。
昔の公式な暦にはなかった?
朝廷や江戸幕府が作ったちゃんとした暦には長い間、不成就日は載っていませんでした。他の有名な吉日や凶日はあったのに、不思議ですよね。
なぜ今、気になるの?
それが現代になって、なぜこんなに知られるようになったのでしょう?詳しい理由は分かりませんが、もしかすると「成就しない」という言葉のインパクトが強く、人々の間で広まりやすかったのかもしれません。
このように不成就日は意外と新しいお日柄なんです。このことを知るだけでも、「そんなに気にしなくてもいいのかも」と、少し気持ちが軽くなるかもしれませんね。
不成就日は気にしなくていい7つの理由
1. 迷信深い平安貴族も気にしてなかったから

不成就日は意外と歴史が浅いです。
平安時代には公家たちが様々な吉日凶日をすごく気にして陰陽師に毎日の過ごし方まで聞いていました。でもそんな怖がりの平安貴族も不成就日は気にしてませんでした。天赦日やたくさんの吉日凶日は朝廷の作った暦にも載っています。でも平安時代には不成就日はありませんでした。
不成就日ができたのは朝廷が力を失い地方で勝手な暦を作るようになってから。地方の暦に載ったことはあったようですが。全国的に広まっってはいません。民間の占い師かだれかがいい出したようです。
結局、不成就日は朝廷や幕府の作った暦には載ってませんでした。ところが現代の誰かが復活させ暦に載せました。
伝統があればいいというものではありませんけれど。そんなあいまいで信憑性の低いものを信じる必要があるでしょうか?
信じて楽しいものなら信じてもいいのですけれど。わざわざ悪くなるものを信じるなんて馬鹿げていると思いませんか?
2. 科学的な根拠信はないから
スピリチュアルなテーマなのに科学を持ち出すのは場違いかもしれません。
でもあえて書きます。
当たり前ですけれど不成就日には科学的に根拠がありません。不成就日が悪いという証拠もありません。統計データなどを分析しても不成就日と物事の吉凶の間に明確な相関関係はないのです。
不成就日だから「全員運が悪い」なんてことはありません。
3. 無駄なストレスになるから
不成就日を気にしすぎるとそれがかえって不安やストレスになります。本当は感じなくていい不安やストレスを作ってしまってるのです。そうなると精神的にも不安定になったり、判断が鈍るかも知れません。
逆に不成就日を気にせずに行動すれはポジティブな気持ちで物事に取り組むことができます。
必要のない重りを背負う必要はないのです。
4. チャンスを逃すから
カレンダーに書かれた不成就日を避けてばかりいると、せっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。人生には良いことも悪いことも起こるものです。不成就日を恐れてばかりいて行動を起こさなかったら、本来あなたのものになったはずのチャンスが逃げてしまうかも知れません。
まして。しなければいけないことや用事を不成就日だからという理由で止めてしまっては意味がありません。
積極的に行動することでより多くの経験を積み成長することができます。
5. 結果だけでなく過程も大切だから
目標を達成するためには私たちは様々な努力をします。その過程で多くのことを学び経験することができます。たとえ目標を達成できなかったとしても、その過程で得たものは決して無駄ではありません。むしろ次の挑戦への糧となります。
何かうまくいかなかっても結果の○✕だけにとらわれるのではなく。原因を分析してみましょう。こうしたらこうなった。こういう発見があった。と新しい知識や経験が身につきます。
でも失敗を運勢に責任転嫁していたら成長はありません。せっかくの知識や経験を逃がしてしまうことになります。もったいないです。
6. 時代が変わったから
不成就日は室町~江戸時代の封建社会の迷信です。
もちろん昔の知識でも良いものなら利用すればいいです。だからこのサイトでも様々なものを紹介しています。
でも悪くなるものをあえて信じる必要はありません。現代では個人の自由や平等が大切にされていますから、過去の迷信にとらわれる必要はないのです。
そんなものを信じるのは「古臭い」「時代遅れ」「格好悪い」「ダサい」「イケてない」そう思えばいいのですね。
7. 自分で考えられる人間になりたいから
不成就日を気にするかどうかは、あなた自信が決めること。でも不成就日を気にするのは不安があるからでしょう。不安があるのは自信がないからです。
占いはときには頼りになりますが。それに頼りすぎるのも考えもの。
占いは頼りすぎると自分で考えることのできない人間。無責任な人間になってしまいます。
周りの意見に流されることなく、あなた自身の軸を持って行動することが大切です。
3.【具体例】不成就日に「避けるべき」と言われる行動
不成就日には、「これをするとうまくいかないのでは?」と昔から言われている行動がいくつかあります。これらはあくまで一般的な考え方として、「そういう説があるんだな」と参考に見てみましょう。
一般的に避けた方が良いとされがちなのは人生の新しいスタートや大きなお祝い事などです。
結婚や入籍
「成就しない」という文字通り、夫婦の新しい始まりには向かない、と言われることがあります。
新しい契約や開店・開業
事業や取引のスタートが順調に進まないかもしれない、と考えられがちです。
引っ越しや移転: 新しい場所での生活や仕事がうまくいかないのでは、と心配されることがあります。
願い事や神社参拝
せっかくお願いしても叶いにくい日、と言われることがあります。
高額な買い物
特に長く使うもの(家、車、家具など)や、お財布のように金運に関わるものは避ける人もいます。
子供の命名
新しい名前での人生のスタートが滞るのでは、と気にする方がいます。
繰り返しになりますが、これらはあくまで昔からの言い伝えや俗説です。「気にしない」という選択をする方もたくさんいらっしゃいますので、必要以上に心配しないでくださいね。
4【具体例】不成就日に「やってもいい」と言われること・おすすめの過ごし方
逆に、不成就日だからといって何もできないわけではありません。実は不成就日でも問題ないとされることや、むしろこの日にすると良い、という考え方さえあるのです。
不成就日をネガティブではなく、少し立ち止まったり整理したりする日にしてみるのはいかがでしょう。
いつもの日常を過ごす
普段通りの仕事や家事、すでに習慣になっていることなどは、特に問題ないと言われています。特別なことをせず、普段通り過ごすのが一番、という考え方もあります。
休息やリラックス
何か新しいことをするより、心と体をゆっくり休ませるのに良い日と捉えることができます。静かに過ごし、疲れを癒す時間に充てましょう。
物事を「終わらせる」
不成就日は、逆に「終わり」に関することには向いている、という少し変わった考え方をする人もいます。例えば、契約の解除や、関係性の見直し、お葬式などが挙げられることがあります。
計画を立てる
具体的な行動を起こす日ではなく、将来の目標や計画をじっくり考えたり、リストアップしたりする時間にするのはおすすめです。
自分を振り返る時間
内省したり、読書や勉強で知識を深めたりと、自分自身と向き合う時間に使うのも良いでしょう。
不成就日を「何もうまくいかない日」と決めつけず、工夫次第で有意義に過ごすことができます。「今日は少しゆっくりしようかな」「計画を立ててみようかな」と、ポジティブに捉えてみてくださいね。
不成就日と大安や一粒万倍日が重なったらどうなる?
不成就日と聞くと不安になるかもしれませんが、この日に「大安(たいあん)」や「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」、「天赦日(てんしゃび)」といった吉日が重なることがあります。
吉日と凶日が重なった場合の考え方
縁起の良い日と悪い日が重なったら、どうなってしまうのだろう?と不思議に思いますよね。
一般的には「強い吉日が凶日の影響を打ち消す」と考えられています。特に不成就日は、これまでに紹介したように歴史が浅く根拠も弱いです。
ですから天赦日や一粒万倍日のような、より強く縁起が良いとされる吉日の効果が優先される、と考えることができます。
重なっても気にしすぎなくて大丈夫
もし不成就日と吉日が重なっていても、必要以上に心配することはありません。せっかくの良いお日柄なのですから、そちらの意味合いを大切にして、前向きに過ごすのがおすすめです。
神社に参拝してはいけない・願いをしてはいけないの?
不成就日の効果?に「願い事がかなわない」と書いてあることがあります。
「それなら神社に行ってお願いしても叶えてもらえないの?」
「参拝してはいけないの?」
と思うかもしれません。
安心してください。不成就日だからといって神様が願いを聞き届けてくれない。なんてことはありません。不安に思うなら神社に行って聞いてみてくださいね。
神社には厄払いに行ったりしますよね。良くなるように願ったり、厄を落としたり。方位除けをしたり。
むしろ悪いことが起きないように力を貸してくれるのが神様です。暦の吉凶は気にしません。むしろ暦の吉凶より、あなたのやる気や行いの方が大事です。
もしあなたの願いが叶わなかったのなら暦ではなく別の理由があるはずです。
あなたの努力が足りないのかもしれませんし。普段の行いやお願いの仕方に理由があるのかもしれません。
決して不成就日のせいではありません。
凶日の本当の意味、そして現代の捉え方
そもそも、なぜ不成就日のような「凶日」という考え方が生まれたのでしょうか?そこには昔の人々の生活の知恵が関係しているのかもしれません。
昔の知恵としての「凶日」
今のように休日が定まっていない時代。人々は毎日働き詰めでした。そんな中で「この日は無理せず休もう」「注意して過ごそう」といった、生活にメリハリをつけるためのサインとして、凶日が生まれたという考え方があります。
不成就日も、もしかすると「ちょっと立ち止まる日」としての役割を持っていたのかもしれません。
現代における不成就日の捉え方
しかし現代は、しっかりと休日があり情報も多く昔とは生活スタイルが大きく変わっています。
だからこそ不成就日を「何もうまくいかない悪い日」と捉える必要はありません。
「今日は不成就日だから、頑張りすぎず休息しよう」「普段はやらない、内省する時間にあててみよう」というように、自分自身と向き合ったり、心と体を休ませたりする良い機会と考えることができます。
ネガティブな日ではなく、自分を大切にするための日として活用するのも一つの賢い方法です。
結論:不成就日に振り回されないために
ここまで、不成就日の由来や気にしなくていい理由、そして現代での捉え方についてお話ししてきました。
大切なのは「自分で決める」こと
結局のところ、不成就日をどう捉え、どう過ごすかは、あなた自身が決めることです。必要以上に恐れたり、迷信に振り回されたりする必要はありません。
大切なのは吉日凶日一喜一憂するのではなく自分で考え、自分の心に従って行動することです。不成就日を上手に受け止めて、あなたのペースで毎日を大切に過ごしてくださいね。あなたの人生は、あなた自身の選択で豊かになっていくのですから。
もっと詳しく知りたい方へ
不成就日の具体的な日付や、他の吉日についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
・不成就日と一粒万倍日や大安・天赦日が重なったらどうなるの?

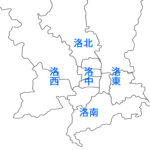

コメント