夜空を見上げたときにひときわ目立つ七つの星の並び、それが北斗七星です。
柄杓(ひしゃく)のような特徴的な形は、あなたもご存知ですよね。でも、この美しい星並びが単なる星座の一部ではないとしたら?
北斗七星には古来より世界中の人々が注目して様々な意味を見出してきました。歴史上の信仰、神話、そしてスピリチュアルな側面まで。
この記事では「北斗七星の意味」を深掘りし、その謎めいたベールを剥がしていきます。読み終える頃には、いつもの夜空が全く違って見えるかもしれません。
さあ、一緒に北斗七星の奥深い世界を探検してみましょう。
「北斗七星」とは?まずは基本を知ろう
夜空に輝く北斗七星とはどのような星の集まりなのでしょうか?まずは、その基本的な特徴や名前の由来や昔から人々の役に立ってきた役割について見ていきましょう。
ひしゃくの形とその正体(おおぐま座の一部)
北斗七星は夜空でひときわ目立つ七つの明るい星が、まるで柄杓(ひしゃく)のように並んだ形をしています。この独特の形は一度見たら忘れられられませんよね。
実は、北斗七星そのものは星座ではなく、「おおぐま座」という大きな星座の一部になります。おおぐま座の腰から尻尾にかけてを構成する星の並びなんですね。
このように星座の一部を構成する特徴的な星の並びを「アステリズム」と呼びます。北斗七星は、アステリズムの代表格と言えるでしょう。
なぜ「北斗七星」と呼ばれるの?名前の由来
「北斗七星」という名前は、古代中国で名付けられたと言われています。北の空にある七つの星が、「斗(ひしゃく)」の形をしていることから、「北斗七星」と名付けられました。漢字の「斗」には、文字通り「ひしゃく」という意味があるんです。
この名前は飛鳥時代に天文学と一緒に日本にも伝わってきたとされています。世界中で様々な呼び方がありますが、「ひしゃく」や「おおぐま」に例えられることが多いのも面白い点です。
「北極星」を見つけるための重要な星
北斗七星は、私たちにとって非常に実用的な役割も果たしてきました。それは、北極星を見つけるための目印になることです。
北斗七星のひしゃくの「水をすくう側」の先端にある二つの星(ドゥーベとメラク)を結び、その方向へ約5倍ほど延長したところに、ひときわ輝く星が見つかります。それが北極星です。北極星は真北の空にほとんど動かず輝いているため、北斗七星は古来から方角を知るための重要な道しるべとして、旅人や船乗りに利用されてきたのです。
季節ごとの見え方の変化
北半球の中緯度地域であれば、北斗七星は基本的に一年中、夜空に見ることができます。ただし、時間帯や季節によって、空のどのあたりに見えるか、また柄杓の向きがどのように変わるかが異なります。
これは地球の自転や公転によるものですが、この柄杓の向きの変化を観察することで、およその時刻や季節を知ることも可能でした。星空は、まさに昔の人々にとって天然の時計でありカレンダーだったと言えるでしょう。
古代から現代へ 日本に伝わる「北斗七星」の意味
北斗七星は、天文学的な役割だけでなく、日本においても古くから人々の信仰の対象とされてきました。特に「北辰信仰」として発展し、私たちの文化や歴史に深く根ざしています。
運命と寿命を司る「北辰信仰」の歴史
日本では古来より、北斗七星や北極星を神格化し、長寿や国家の安泰、個人の幸福を祈る「北辰信仰(ほくしんしんこう)」が盛んに行われてきました。奈良時代にはすでにその信仰が庶民の間にも広まっていたと言われています。
この信仰の源流は、古代中国の思想にあります。宇宙の中心には「天帝(天皇大帝)」という至高の存在がおり、地上世界や生きとし生けるものの運命を司っていると考えられていました。その天帝がいる星が北半球の空の中心でほとんど動かない北極星だとされたのです。
天帝、北極星、そして北斗七星の関係性
中国の思想では、北極星(天帝)は宇宙の不動の中心ですが実際に地上の生命や運命に直接働きかけるのは、その周囲を巡る北斗七星だと考えられました。北斗七星は天帝の命令を受け人間の寿命や吉凶禍福を管理する役割を担っているとされたのです。
私たちの人生に直接影響を与えているのは北斗七星だと信じられていました。そのため、天帝と北斗七星に祈ることで運命を好転させたり、寿命を延ばしたりすることができるという信仰が生まれ広く受け入れられていったのです。
陰陽道や密教における「北斗七星」の重要性
中国から伝わった北辰信仰は日本独自の発展を遂げました。特に陰陽道や密教といった思想・宗教に取り入れられ、重要な位置を占めるようになります。
陰陽道では、北斗七星は強力な力を持つ星として、災難除けや病気平癒、延命などの祈祷の対象とされました。密教では、北極星や北斗七星は妙見菩薩(みょうけんぼさつ)という仏様と結びつけられ、そのご利益が信仰されました。
神道においても、宇宙の根源神とされる天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)が北極星や北斗七星を司る神様とされ、信仰の対象となっています。
庶民から武士まで広まった「北辰信仰」のエピソード
北辰信仰は、平安時代の貴族たちが日々の祈りの中で北斗七星に長寿や無病息災を願ったように、時の権力者だけでなく、庶民の間でも篤く信仰されました。庶民はもっとシンプルに日々の幸福や長生きを願って北斗七星に祈りを捧げました。
また、戦乱の世においては、妙見菩薩を信仰する武士が多くいました。例えば千葉氏などの桓武平氏の流れを汲む武士団は妙見信仰を氏神とし、戦勝や武運長久を祈りました。これは、北辰(北極星・北斗七星)が天の中心であり、決して揺るがない絶対的な存在であることから、武士たちが己の信念や一族の繁栄を重ね合わせたためと考えられています。
現在も残る「北斗七星」を祀る場所
北辰信仰や妙見信仰は、形を変えながらも現代に受け継がれています。京都にある大将軍八神社のように、陰陽道の星の神様として北斗七星や守護星のお守りを授与している神社もあります。
また、全国各地に妙見菩薩を本尊とするお寺や、北辰信仰に関連する神社が点在しています。これらの場所を訪れると、いかに北斗七星が日本の歴史や文化、人々の暮らしに深く根ざしてきたかを感じ取ることができるでしょう。
北斗七星は人間の人生を見守る星
日本では古来より北斗七星に長生きや幸福を祈る北辰信仰が盛んでした。奈良時代には庶民の間に広まっていました。
北辰信仰の元になったのは古代中国の信仰です。宇宙の中心には天帝(天皇大帝:てんおうだいてい)がいて地上世界と生き物の運命を決めていると考えられていました。天帝がいる星は北極星と考えられました。北半球の空の中心は北極星の近くだったからです。
北斗七星は天帝を守る星です。でもそれだけではありません。天帝の命令を受けた北斗七星が地上や人間の生命や運命を管理しているのです。
つまり、直接人間の寿命や運命を動かしているのは北斗七星なのです。
天帝と北斗七星にお祈りして運命を良くしたり寿命を伸ばしてもらう信仰が流行りました。それが北辰信仰です。
インドから中国に伝わった密教もこの考えを採用。道教と密教の両方が北極星と北斗七星に願いを伝える技があります。
北辰信仰は日本にも伝わり、陰陽道と密教で北斗七星にお祈りする北辰信仰が流行りました。とくに日本では北斗七星への信仰が人気を集めます。
北斗七星に祈れば 災難にもあわず、寿命が伸びる。とされたのです。
北辰信仰は天皇や公家だけでなく庶民にも人気でした。庶民はもっと単純に北斗七星に祈って幸福と長生きを願いました。
密教では妙見菩薩、神道では天之御中主神が北斗七星と北極星を司る神様です。
あなたの運命を握る北斗七星
北辰信仰では人間一人一人に守護星がついています。北斗七星の7つの星の中から必ずどれかの星がその人の守護星になるのです。
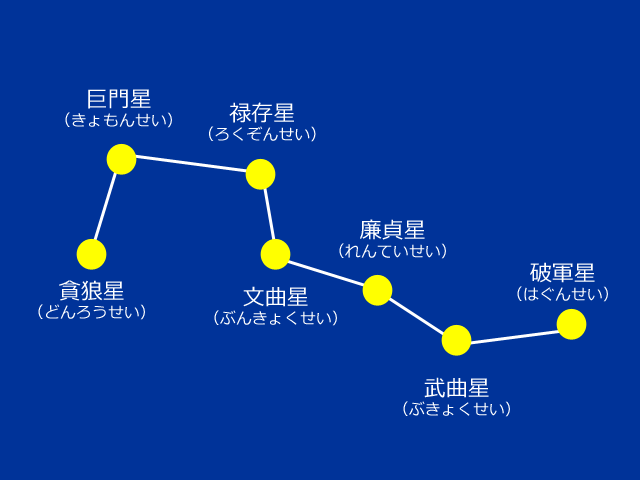
柄杓のような形の先頭から、貪狼星(どんろうせい)、巨門星(きょもんせい)、禄存星(ろくぞんせい)、文曲星(ぶんきょくせい)、廉貞星(れんていせい)、武曲星(ぶきょくせい)、破軍星(はぐんせい)と名前がついています。
どの星が守護星になるかは生まれ年の十二支で決まります。
十二支の守護星
守護星 干支
貪狼星(とんろうせい) ねずみ
巨門星(きょもんせい) うし、いのしし
禄存星(ろくぞんせい) とら、いぬ
文曲星(ぶんきょくせい) うさぎ、とり
廉貞星(れんていせい) たつ、さる
武曲星(ぶきょくせい) へび、ひつじ
破軍星(はぐんせい) うま
平安時代の貴族たちは毎日、北斗七星にお祈りしました。
その方法を簡単に説明すると。
朝起きたら顔を洗い。天皇大帝と自分の守護星の名を7回唱えるのです。
これを毎日すると、災難(トラブル)を避け、長生きできる。とされました。
その信仰は形を変え現在にも続いています。京都の大将軍八神社のように北斗七星と守護星のお守りを授与している神社もあります。
ギリシア神話の母と子の物語
北斗七星はおおぐま座の一部です。おおぐま座の由来はギリシア神話からきています。
カリストというニンフ(妖精)がいました。カリストは狩猟の女神アルテミスの侍女の一人です。あるとき、神々の王・ゼウスはカリストが好きになりました。ゼウスとカリストの間には子供が生まれます。
すると神々の女王ヘーラーが激怒。カリストを熊に変えてしまいました。
カリストの息子アルカスはニンフのマイヤに育てられました。アルカスは立派な王に成長しました。あるときアルカスが狩りをしていると熊に出会いました。その熊は母カリストでしたがアルカスは気が付きません。熊を仕留めようとしました。それを見たゼウスはアルカスを熊に変え。母と子を空にあげて星にしました。
それがおおぐま座とこぐま座です。おおぐま座は母カリスト。こぐま座は息子のアルカスといわれます。
また。アルカスが変身したのはうしかい座の一等星アルクトウロス(アークトゥルス)ともいわれますが、英語圏や日本ではこぐま座に変身した説が有名です。
季節の変化・自然の循環を意味する星
北斗七星はおおぐま座の一部です。星座はギリシアで決めたものが元になっています。ところがギリシア以外でも北斗七星を「熊」と考えた地域もあります。
北アメリカの先住民族の神話
北アメリカ先住民族は北斗七星を熊と考えていました。部族によって少しずつ話は違いますが、北斗七星を熊や熊に関係する星と考えているのは共通しています。
アベナキ神話
北アメリカの先住民族アベナキ族には北斗七星にまつわる神話があります。
北斗七星の七つの星は熊と3人の狩人を意味します。3人の狩人は毎晩熊を追いかけ、秋に熊を仕留めます。仕留められ逆さに吊るされた熊から血が滴り落ち、地上の葉っぱは赤く染まります。天の神は毎年春になると熊を蘇らせます。そしてまた狩人達の追跡が始まるのです。
イロコイ族も熊と3人の狩人の神話をもちます。
ズニ神話
ズニ族の神話では北斗七星は大きな熊です。熊は北の神から土地を守る守り神。ところが熊は冬になると冬眠します。熊が冬眠している間、北の神が冷ややかな息を土地に吹きかけて地上を荒廃させ作物を枯らします。春になって熊が冬眠から目が覚めると再び北の神から土地を守ります。
どの神話にも共通するのは季節の変化と関連付けていることです。冬がやって来るのはなぜか?冬になると熊がいなくなるのはなぜか?その理由が語られています。
北斗七星は自然のサイクルを意味する星なのです。
スピリチュアルな意味
北斗七星にもスピリチュアル(ニューエイジ)な意味があります。
北斗七星は神様のメッセージを伝える星です。
夜空の北斗七星を見ながら、空に想いをはせてみてはいかがでしょうか?あるいは北斗七星の写真を見ながら瞑想するものもいいかもしれません。
何かインスピレーションが得られるかもしれませんね。
北斗七星はおおぐま座の一部です。おおぐま座はこぐま座とセットになっています。そのため母と子の愛情。親から子への愛情を意味しています。
おおぐま座とこぐま座は片方が直立しているときは片方が逆さまになっていたり。様々な見え方をします。
お互いがバランスを撮っているように見えるため、陰と陽の調和を意味しています。
欧米のスピリチュアルに興味のある人達の間では北斗七星のタトゥーをしたり、お守りをもつ人もいるようです。



コメント
私の上には10月からずっと北斗七星があります。毎朝見てます。私が動けば、北斗七星も必ず私と共に動きます。信じられませんが本当なんです。
北斗七星があなたを見守ってくれているのかもしれませんね。